佐伯泰英著「惜櫟荘だより」岩波書店刊を読了
著者初のエッセイ集、佐伯泰英著「惜櫟荘だより」というハードカバーの本を購入した…。勿論筆者は「居眠り磐音江戸双紙」「酔いどれ小籐次」そして「吉原裏同心」などなど時代小説の売れっ子作家である。本書を手にしたのはそれらの作品にどっぷりと浸かった読者の1人としてその著者に興味を覚えたことが1番の原因である。
ただし本書は小説ではない。岩波書店の創業者岩波茂雄が昭和16年(1941)に建てた熱海の別荘を、作家佐伯泰英が縁あって譲り受けた。別荘の名は惜櫟荘(せきれきそう)という。本書はこの歴史的な建物を完全修復するまでを描いたドキュメントなのだ。
1941年,岩波書店の創業者である岩波茂雄は静養を目的とし,熱海に別荘惜櫟荘を建てた。建築家、吉田五十八が手掛けたその近代数寄屋建築最高峰の家屋を、熱海に仕事場を構えていた佐伯が縁あって譲り受けることになった。
惜櫟荘は引き受け手を探していると聞き「もし開発業者の手に渡ったら二度と残らない」と危惧した佐伯は、別荘を含む土地を私財を投じて購入することになる。
さらに佐伯は建物を後世に残すべく現状保全だけでは満足せず、いったん解体して地盤を整備し耐震工事をした上で建築当時そっくりに復元するという壮大な計画を実行する。
傷みの激しい浴室の床など一部を除き「何もつけ足さず、何も削らない」というコンセプトで、プロジェクトは繊細にかつ大胆に進められた。そうした拘りを実現するため、復元には吉田五十八の教え子である建築家・板垣元彬や、かつて一度修復を手掛けたことがあるという水澤工務店などに依頼することになる。
しかし設計図もない中,手探りで解体・復元作業が進められ、やがて趣向に満ちた建築の創造性が明らかになる…。
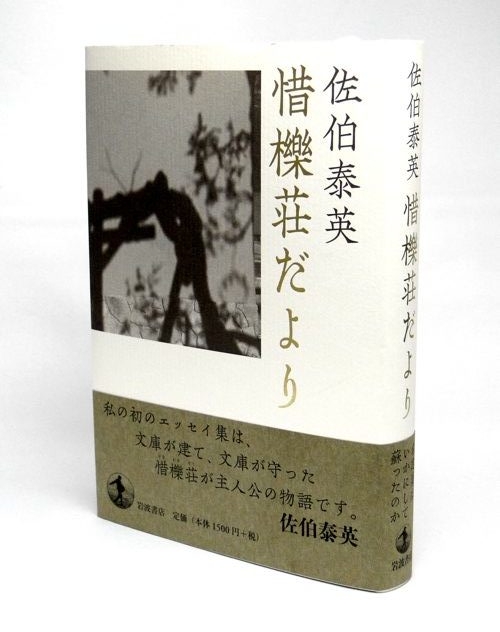
とはいえ特に建築の知識などない私だが、ふと興味を持った要因は建物が岩波書店の創業者の別荘だったということ。そしてげすのかんぐりと承知はしているものの、買取はもとより解体と完全修復と聞き、膨大な金が掛かるはず…。さすがに佐伯は印税で高額な収入を得たに違いないと思いつつ、それに値する建物とはどのようなものなのか…と興味を持った(笑)。
そして「惜櫟荘は文庫で建てられ文庫が守った建物」というコピーにも惹かれた…。
いまでこそ「居眠り磐音江戸双紙」「酔いどれ小籐次」「吉原裏同心」そして「夏目影二郎始末旅」などでベストセラーを続けている佐伯泰英だが、実は遅咲きの人であり57歳で時代小説に転身するまで売れない現代小説の書き手であり、その前は写真家だった。
本書には惜櫟荘とその出会いおよび建物を完全修復するまでの興味深いドキュメントが綴られているわけだが、カメラマン時代、スペインでの生活や当時出会った作家の堀田善衛、英文学者の永川玲二、詩人の田村隆一らのエピソードが合間にはさまれ、佐伯の人生の一端を覗くことができるのも興味深い。特に俳優で読書家としても知られた故児玉清とのエピソードは素敵だった。
さらに知る由もなかったが文庫書き下ろしという出版方法は大手出版社では歓迎されるものではなく佐伯自身、どこか文庫書き下ろしの時代小説という形態に引け目を感じていたという。筆者はあとがきに書いているが、この形態は十数年前までは存在しなかったという。そして文芸書籍が売れなくなった昨今、中堅の出版社が一発勝負の文庫書き下ろしを手がけ、筆者など(本人曰く)売れない作家がこの戦線で生き残りを図ったのが始まりであり「際物出版」だったという。
そのある意味筆者自身が後ろめたくも感じていた文庫書き下ろしだったが十数年書き続けてきた結果、百八十余冊の文庫と累計四千万部という大ベストセラー作家となり、これが惜櫟荘買い取りと修復の原費になった。まさしく「惜櫟荘は文庫で建てられ文庫が守った建物」だということになる。
結果、本書がきっかけとなり佐伯は2014年度の文化賞を日本建築学会から送られることになった。無論それは本書のテーマである惜櫟荘の修復保存とその刊行における建築文化への貢献に対してである。
ともあれ佐伯の小説の中で…例えば「酔いどれ小籐次」では “おりょう” が住み暮らす須崎村の「望外川荘」の描写は日本建築や茶室などに疎い私などにも目の前にその情景が浮かぶような気がするほど生々しい。きっと惜櫟荘の修復修繕の過程で得た知識が作品にも生きているのではないだろうか。
佐伯はいう。「先の希望も見つからず、日々不条理に身悶えし、不安を抱えながら生きている人々に、満員電車の中で読む佐伯ワールドは束の間の救いになればとの信念で書いている」と…。そして最も多く読まれている「居眠り磐音」の主人公・坂崎磐音にしても、親友を斬り、婚約者を失い、故郷を捨てて浪々の身となり様々な苦悩を背負っている…。
磐音は、生きるためとはいえ用心棒やウナギ割きなど何でもしながら、春風のように穏やかなやさしさを失わない人物だ…。日溜りでまどろむ猫のようなと形容される彼は、それでいて滅法強い。そしてさまざまな出来事に翻弄されながら六畳一間の金兵衛長屋で懸命に生き、周辺に住む人情あふれる人たちと接しながら成長していく。その姿に我々は共感を覚え、爽快さ痛快さを感じて読み続けるのだろう。
確かに佐伯の言うとおり、彼の小説にはまっている間は至福のときだ。世間の嫌なことをすべて忘れて佐伯ワールドにのめり込むことができる。
さて、建築のことはほとんど知識のない私だが、このエッセイを読み進むうちに何か大切なことを知り得ているという思いをしてきた。本書のテーマは惜櫟荘という実在する建築物ではあるが、飽きさせないのはさすがである。また時間を作り、ゆっくりと再読してみたいと思っている。
ただし本書は小説ではない。岩波書店の創業者岩波茂雄が昭和16年(1941)に建てた熱海の別荘を、作家佐伯泰英が縁あって譲り受けた。別荘の名は惜櫟荘(せきれきそう)という。本書はこの歴史的な建物を完全修復するまでを描いたドキュメントなのだ。
1941年,岩波書店の創業者である岩波茂雄は静養を目的とし,熱海に別荘惜櫟荘を建てた。建築家、吉田五十八が手掛けたその近代数寄屋建築最高峰の家屋を、熱海に仕事場を構えていた佐伯が縁あって譲り受けることになった。
惜櫟荘は引き受け手を探していると聞き「もし開発業者の手に渡ったら二度と残らない」と危惧した佐伯は、別荘を含む土地を私財を投じて購入することになる。
さらに佐伯は建物を後世に残すべく現状保全だけでは満足せず、いったん解体して地盤を整備し耐震工事をした上で建築当時そっくりに復元するという壮大な計画を実行する。
傷みの激しい浴室の床など一部を除き「何もつけ足さず、何も削らない」というコンセプトで、プロジェクトは繊細にかつ大胆に進められた。そうした拘りを実現するため、復元には吉田五十八の教え子である建築家・板垣元彬や、かつて一度修復を手掛けたことがあるという水澤工務店などに依頼することになる。
しかし設計図もない中,手探りで解体・復元作業が進められ、やがて趣向に満ちた建築の創造性が明らかになる…。
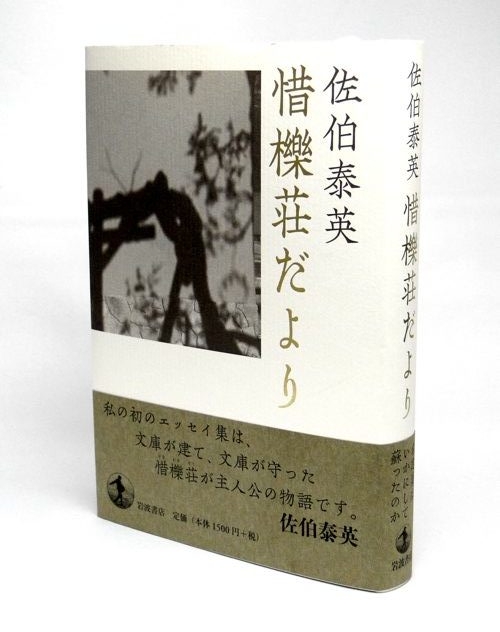
とはいえ特に建築の知識などない私だが、ふと興味を持った要因は建物が岩波書店の創業者の別荘だったということ。そしてげすのかんぐりと承知はしているものの、買取はもとより解体と完全修復と聞き、膨大な金が掛かるはず…。さすがに佐伯は印税で高額な収入を得たに違いないと思いつつ、それに値する建物とはどのようなものなのか…と興味を持った(笑)。
そして「惜櫟荘は文庫で建てられ文庫が守った建物」というコピーにも惹かれた…。
いまでこそ「居眠り磐音江戸双紙」「酔いどれ小籐次」「吉原裏同心」そして「夏目影二郎始末旅」などでベストセラーを続けている佐伯泰英だが、実は遅咲きの人であり57歳で時代小説に転身するまで売れない現代小説の書き手であり、その前は写真家だった。
本書には惜櫟荘とその出会いおよび建物を完全修復するまでの興味深いドキュメントが綴られているわけだが、カメラマン時代、スペインでの生活や当時出会った作家の堀田善衛、英文学者の永川玲二、詩人の田村隆一らのエピソードが合間にはさまれ、佐伯の人生の一端を覗くことができるのも興味深い。特に俳優で読書家としても知られた故児玉清とのエピソードは素敵だった。
さらに知る由もなかったが文庫書き下ろしという出版方法は大手出版社では歓迎されるものではなく佐伯自身、どこか文庫書き下ろしの時代小説という形態に引け目を感じていたという。筆者はあとがきに書いているが、この形態は十数年前までは存在しなかったという。そして文芸書籍が売れなくなった昨今、中堅の出版社が一発勝負の文庫書き下ろしを手がけ、筆者など(本人曰く)売れない作家がこの戦線で生き残りを図ったのが始まりであり「際物出版」だったという。
そのある意味筆者自身が後ろめたくも感じていた文庫書き下ろしだったが十数年書き続けてきた結果、百八十余冊の文庫と累計四千万部という大ベストセラー作家となり、これが惜櫟荘買い取りと修復の原費になった。まさしく「惜櫟荘は文庫で建てられ文庫が守った建物」だということになる。
結果、本書がきっかけとなり佐伯は2014年度の文化賞を日本建築学会から送られることになった。無論それは本書のテーマである惜櫟荘の修復保存とその刊行における建築文化への貢献に対してである。
ともあれ佐伯の小説の中で…例えば「酔いどれ小籐次」では “おりょう” が住み暮らす須崎村の「望外川荘」の描写は日本建築や茶室などに疎い私などにも目の前にその情景が浮かぶような気がするほど生々しい。きっと惜櫟荘の修復修繕の過程で得た知識が作品にも生きているのではないだろうか。
佐伯はいう。「先の希望も見つからず、日々不条理に身悶えし、不安を抱えながら生きている人々に、満員電車の中で読む佐伯ワールドは束の間の救いになればとの信念で書いている」と…。そして最も多く読まれている「居眠り磐音」の主人公・坂崎磐音にしても、親友を斬り、婚約者を失い、故郷を捨てて浪々の身となり様々な苦悩を背負っている…。
磐音は、生きるためとはいえ用心棒やウナギ割きなど何でもしながら、春風のように穏やかなやさしさを失わない人物だ…。日溜りでまどろむ猫のようなと形容される彼は、それでいて滅法強い。そしてさまざまな出来事に翻弄されながら六畳一間の金兵衛長屋で懸命に生き、周辺に住む人情あふれる人たちと接しながら成長していく。その姿に我々は共感を覚え、爽快さ痛快さを感じて読み続けるのだろう。
確かに佐伯の言うとおり、彼の小説にはまっている間は至福のときだ。世間の嫌なことをすべて忘れて佐伯ワールドにのめり込むことができる。
さて、建築のことはほとんど知識のない私だが、このエッセイを読み進むうちに何か大切なことを知り得ているという思いをしてきた。本書のテーマは惜櫟荘という実在する建築物ではあるが、飽きさせないのはさすがである。また時間を作り、ゆっくりと再読してみたいと思っている。
- 関連記事
-
- 古楽情報誌「アントレ」に掲載されたクリス・エガートン へのインタビューを読んで (2014/10/29)
- 歴史の輪を探る? タロットカードの秘密 (2014/10/10)
- イングリッシュパブ 「シャーロック・ホームズ」でランチを! (2014/10/01)
- お宅のエアコン、ボコボコと異音しませんか? (2014/09/26)
- 石田伸也著「ちあきなおみに会いたい。」徳間文庫刊再読と彼女の歌声に酔う (2014/09/19)
- 佐伯泰英著「惜櫟荘だより」岩波書店刊を読了 (2014/09/10)
- 佐伯泰英氏の時代小説「吉原裏同心」の魅力 (2014/09/01)
- イメージ・グラフィズム「眼の劇場〜image&imagination」 (2014/07/30)
- 「大塚国際美術館 ひとり旅」特設ページ (2014/06/29)
- 本当に昔はよかったのか? (2014/06/18)
- 伊勢木綿再び〜今度は手拭いを購入 (2014/05/28)





